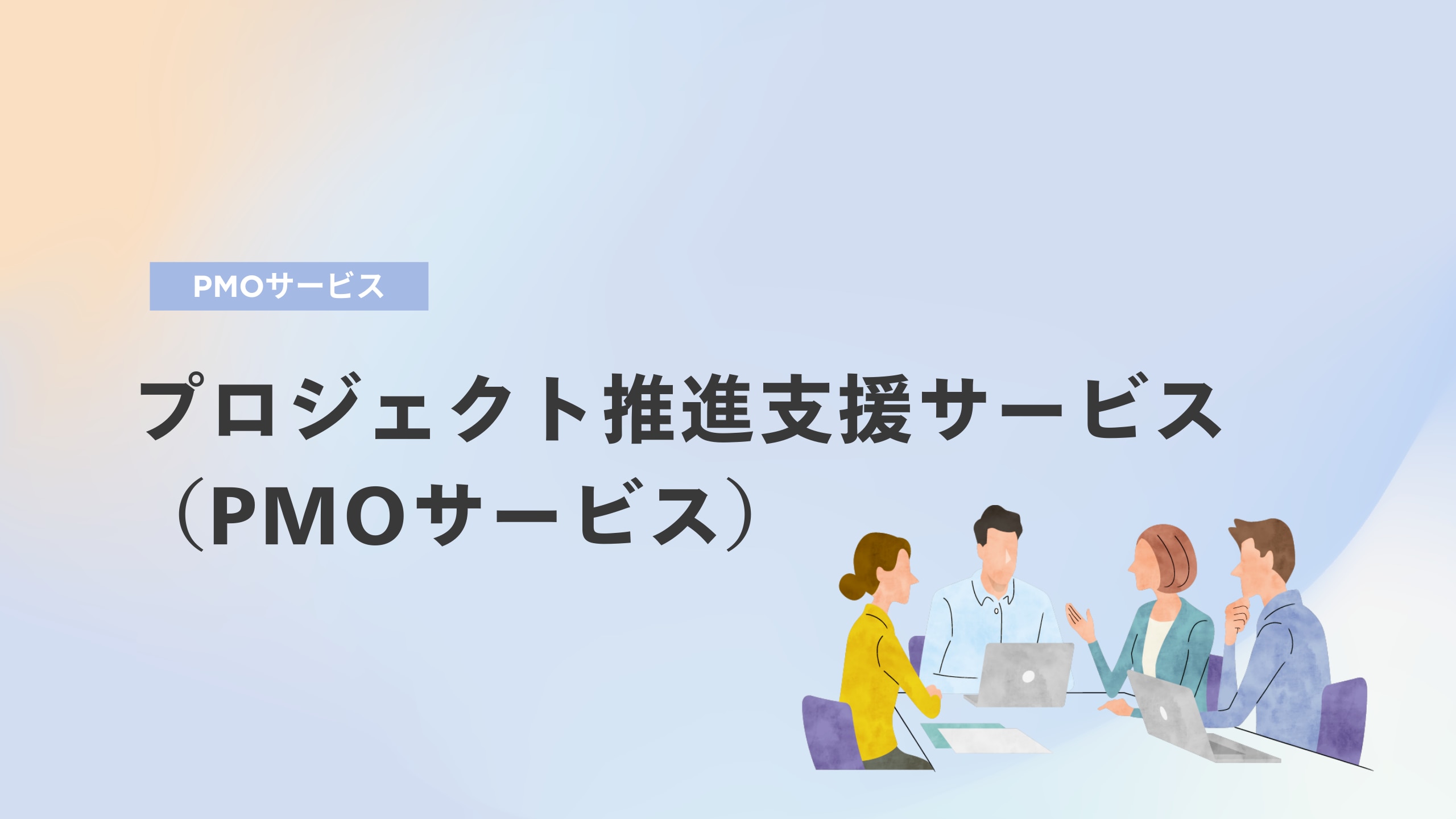現場で使える人材育成プロセス。実践的スキルが定着するカリキュラム設計
多くの企業が、せっかく素晴らしい研修を実施しても「研修内容は良いはずなのに、なぜか現場でスキルが活用されない」という普遍的な悩みを抱えています。
人事・育成担当者の皆様の中には、「研修が単発のイベントで終わってしまい、時間とコストをかけた投資対効果を経営層に説明できない」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、そのような課題を解決し、社員のスキルを確実に現場へ定着させるための体系的な「4ステップの人材育成プロセス」と、実践的なカリキュラム設計のポイントを徹底的に解説します。
この記事をお読みいただくことで、貴社の人材育成施策の成果を最大化し、社員が自律的に成長する「自走できる組織」を築き上げる具体的な道筋が見えてくるでしょう。
目次[非表示]
- ・なぜ人材育成は「現場で使えない」で終わるのか?よくある3つの失敗パターン
- ・現場で使える人材育成の全体像|スキル定着をゴールにした4ステッププロセス
- ・ステップ1:現状把握と課題の可視化(アセスメント)
- ・ステップ2:育成ゴールと目指すべき人材像の具体化
- ・ステップ3:スキル定着を促す実践的カリキュラムの設計
- ・ステップ4:効果測定と継続的な改善サイクル(PDCA)
- ・【手法別】実践的スキルを定着させるカリキュラム設計のポイント
- ・【階層・目的別】カリキュラム設計の具体例
- ・人材育成を成功に導く組織的な仕組みづくり
- ・外部パートナーの活用で人材育成を加速させるという選択肢
- ・まとめ
- ・「自走できる組織」づくりを実現するデジタル人材育成サービス(株式会社システナ)
なぜ人材育成は「現場で使えない」で終わるのか?よくある3つの失敗パターン
多くの企業が人材育成に多大なコストと時間を投じていますが、「期待した効果が得られない」「現場でスキルが活用されない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。
これは、育成担当者が陥りがちな、いくつかの「失敗パターン」が存在するためです。
このセクションでは、人材育成においてよく見られる3つの失敗パターンを具体的に掘り下げて解説します。
自社の人材育成施策と照らし合わせながら読み進めていただくことで、現状の課題を客観的に把握し、より実践的な改善策を検討するきっかけになるでしょう。
失敗パターン1:研修が単発のイベントで終わってしまう
人材育成における最も一般的な失敗の一つが、研修を実施すること自体が目的となってしまい、学習した内容が実務に結びつかないケースです。
せっかく時間とお金をかけて研修を受けても、その場限りの「単発イベント」で終わってしまっては、本当の意味でのスキル定着にはつながりません。
この問題の根源には、研修後のフォローアップが不足していることが挙げられます。
研修で得た知識やスキルは、「学びの忘却曲線」が示すように、時間が経つとともに薄れていくものです。
実践課題の提供、定期的な進捗確認、きめ細やかなフィードバックといった研修後の支援がなければ、学習効果はあっという間に失われてしまいます。
「研修が単発で終わり、現場に定着しない」という課題の背景には、学習したスキルを現場で試す機会の欠如や、実践をサポートする仕組みが整っていないという根本的な原因があります。
研修内容が現場で活かされるためには、学びと実践が一体となった継続的なプロセスが不可欠です。
失敗パターン2:実務と乖離した内容で学習意欲が湧かない
研修内容が受講者の日常業務と大きくかけ離れていたり、抽象的すぎたりすると、社員の学習意欲を引き出すことは困難です。
「このスキルが自分の仕事にどう役立つのか」という具体的なイメージが持てなければ、受講者は受け身の姿勢になり、結果として学習効果は半減してしまいます。
特に、実践的な学習を好む社員にとって、座学中心で現実味のない研修は退屈に感じられ、学習に対するモチベーションを低下させてしまう原因となります。
業務に直結しないと感じる内容は、貴重な業務時間を割いてまで学ぶ価値がないと判断されてしまいかねません。
このような事態を避けるためには、カリキュラム設計の段階で、現場の具体的な業務課題や、実際に使用しているツールを題材にするなど、実践的な内容を盛り込むことが不可欠です。
受講者が「これは自分の仕事に直接活かせる」と実感できる内容にすることで、自律的な学習を促し、スキルの定着へとつなげることができます。
失敗パターン3:効果測定が曖昧で投資対効果を説明できない
人材育成施策のもう一つの失敗パターンとして、効果測定が曖昧である点が挙げられます。
研修直後のアンケートで「満足度」が高くても、それが実際の業務改善や業績向上に繋がっているのか、客観的に評価する仕組みがなければ、施策の真の価値は測れません。
「研修効果の定量化が難しく、上層部に説明しにくい」という課題は、多くの育成担当者が直面する問題です。
行動変容や業績への貢献度といった客観的な成果を測定する指標がなければ、育成への投資が正当であったことを経営層に理解してもらうことは困難になります。
具体的な測定指標、例えば「特定の業務にかかる時間の削減率」「生産性の向上率」「エラーの発生件数」などを設定し、育成の投資対効果(ROI)を可視化することが重要です。
効果測定の仕組みがなければ、施策の継続や拡大の承認を得ることが難しくなり、結果として企業の成長を阻害する要因にもなりかねません。
現場で使える人材育成の全体像|スキル定着をゴールにした4ステッププロセス
人材育成において、「研修内容は良いはずなのに、現場でスキルが活用されない」という悩みを抱えている方も多いと思います。
研修が単発のイベントで終わってしまい、投資対効果を経営層に説明できないといった課題は、多くの人事・育成担当者が直面している共通のものです。
このセクションでは、そうした課題を解決し、スキル定着と現場での成果創出を実現するための体系的なアプローチとして、「4ステップの人材育成プロセス」をご紹介します。
これから解説する4つのステップは、現状把握と課題の可視化から始まり、育成ゴールの具体化、実践的なカリキュラム設計、実行と伴走支援、そして効果測定と改善までを一貫してカバーします。
それぞれのステップの目的と具体的な進め方を理解することで、場当たり的ではない、戦略的な人材育成を可能にし、社員が自律的に成長する「自走できる組織」へと貴社を導く道筋が見えてくるでしょう。
ステップ1:現状把握と課題の可視化(アセスメント)
人材育成プロセスにおける最初の重要なステップは、現状を正確に把握し、育成すべき課題を客観的に可視化することです。
「何となくスキルが不足している」「この研修が必要だろう」といった思い込みや感覚に頼るのではなく、データに基づいた分析が不可欠です。
具体的な手法としては、スキル診断テスト、従業員や管理職への詳細なヒアリング、あるいは実際の業務プロセスをモニタリングするといった方法が挙げられます。
これにより、「あるべき人材像」と「現状のスキルレベル」との間に存在する具体的なギャップが明確になり、どのスキルを優先的に、どのように育成すべきかという悩みに明確な答えを導き出すことができます。
ステップ2:育成ゴールと目指すべき人材像の具体化
現状把握で見えてきた課題に基づき、人材育成の具体的なゴールを設定します。
このステップでは、曖昧な目標ではなく、誰が、いつまでに、何を、どのレベルまでできるようになるのかを明確に定義することが極めて重要です。
例えば、「全社員のITリテラシーを向上させる」といった漠然とした目標ではなく、「3ヶ月後までに、営業部門の50%がBIツールで自身の担当顧客の売上データを可視化し、週次報告に活用できる」のように、具体的な行動と成果に焦点を当てます。
この育成ゴールは、必ず経営戦略や事業目標と連動している必要があり、経営層、現場、人事部門といった関係者間で共通認識を持ち、合意形成を図ることが不可欠です。
具体的なゴールを設定することで、育成施策の方向性が明確になり、後のカリキュラム設計や効果測定の基準となります。
ステップ3:スキル定着を促す実践的カリキュラムの設計
設定した育成ゴールを達成するための具体的な学習計画、すなわちカリキュラムの設計は、人材育成プロセスの心臓部ともいえるフェーズです。
ここで重要なのは、「実務との乖離」というよくある失敗パターンを避けることです。
受講者が「このスキルは自分の仕事に直接役立つ」と実感できるような、実践的な内容を盛り込む必要があります。
具体的には、実際の業務で直面する課題を題材にしたケーススタディや、ツールを操作しながら学ぶハンズオン形式の研修を積極的に取り入れることが効果的です。
例えば、Power BIやPower Appsなどのツール研修では、ただ操作方法を教えるだけでなく、自社のデータや業務フローを題材にした演習を取り入れることで、学習効果を飛躍的に高めることができます。
さらに、研修(Off-JT)だけで完結させるのではなく、実務での実践(OJT)や自学自習(自己啓発)を組み合わせることが重要です。
研修の前後には、受講者自身に「何を学び、それをどのように実務で活かすか」という具体的な課題を設定させることで、学びを一過性のものにせず、実務へと繋げる「ブレンディッドラーニング」の考え方をカリキュラム全体に組み込みます。
これにより、受講者は能動的に学習に取り組み、習得したスキルを現場で実際に活用する意欲を高めることができるでしょう。
ステップ4:効果測定と継続的な改善サイクル(PDCA)
人材育成プロセスを完結させ、次なる改善へと繋げるための最終ステップは、施策の効果を測定し、継続的な改善サイクルを回すことです。
「効果測定が曖昧」という失敗パターンを克服するためには、ステップ2で設定した育成ゴールに基づき、成果を客観的に評価する仕組みが不可欠となります。
測定すべき指標としては、大きく3つのレベルで評価することが有効です。
❶:研修直後の「理解度テスト」による知識定着の確認
❷:実務での「行動変容」、例えばツールの利用頻度や特定の業務にかかる時間の変化など
❸:業務成果への「貢献度」、具体的には業務時間削減率や生産性向上率、
エラー発生件数の減少といったROI(投資対効果)に直結する指標
これらの測定結果を分析し(Check)、カリキュラムの内容や支援方法、運用体制などを見直す(Action)というPDCAサイクルを回し続けることで、育成施策は継続的に進化し、より高い効果を生み出すことが可能になります。
またこれらのステップをすべて自社でやり切るのが難しい場合は、伴走型で支援を行うベンダーを活用し、研修後の技術的なQ&Aサポート体制の構築、定期的な進捗確認や実践アドバイス、さらには人材育成プロジェクト全体の管理支援などを支援してもらうのも一つの手段です。
【手法別】実践的スキルを定着させるカリキュラム設計のポイント
人材育成の全体像と、スキル定着をゴールにした5ステップのプロセスをご理解いただいたところで、ここからは具体的な育成手法に焦点を当てていきます。
育成の目的や対象者によって最適な手法は異なり、それらを適切に組み合わせることが学習効果を最大化する鍵となります。
このセクションでは、代表的な育成手法である「Off-JT」「OJT」「自己啓発」「メンター制度・コーチング」を取り上げ、それぞれの特徴と、学習効果を最大化してスキルを確実に定着させるためのポイントを詳しく解説していきます。
自社の人材育成において、どの手法をどのように活用すべきかのヒントを見つけていただければ幸いです。
Off-JT(Off-the-Job Training - 研修)
OJT(On-the-Job Training - 実践)
OJT(On-the-Job Training)は、明確な育成計画に基づく実践的な指導手法であり、Off-JT(座学研修)で得た知識を実務で応用する最適な機会です。
効果的なOJT運用のポイントは、以下の3点です。
❶:具体的な目標と期間を定めた「OJT計画書」の作成
❷:指導者(トレーナー)への適切なコーチング・フィードバック研修
❸:定期的な1on1ミーティングを通じた進捗確認と丁寧なフィードバック
特に、Off-JTで学んだ理論をOJTで実践する機会を意図的に設けることで、学習定着と実務応用力が向上し、OJTとOff-JTの密接な連動により学習効果は飛躍的に高まります。
自己啓発(SD)
自己啓発は、社員の自発的な学習意欲を会社が支援し、組織全体の成長と従業員エンゲージメント向上に繋がる重要な要素です。
企業は、書籍購入補助、資格取得報奨金、eラーニング提供、社内勉強会支援などで、社員が興味やキャリアパスに合わせて学習できる環境を整備することが重要です。
しかし、インプットだけでなく、学んだ知識・スキルを活かす「アウトプットの機会」(新プロジェクト参加、学習内容共有、新役割への挑戦など)が不可欠です。
これにより、学習は自己満足で終わらず組織の力へと転換され、自律的な学習と実践が相乗効果を生み、個人と組織の発展を加速させます。
メンター制度・コーチング
メンター制度やコーチングは、1対1の対話で個人の成長をきめ細やかに支援する効果的な手法です。
スキル習得だけでなく、業務やキャリアの悩み、精神的サポートも提供し、従業員のエンゲージメント向上や早期離職防止に貢献します。
効果的な運用には、メンターとメンティーの相性を考慮したマッチングが不可欠で、これにより信頼関係を築きオープンな対話を促進します。
また、メンター自身の傾聴力・フィードバックスキル向上トレーニングも重要で、メンティーの自律的な成長を促します。
さらに、定期的な面談が形骸化しないよう、アジェンダ設計の工夫や人事部門によるサポート体制構築が重要です。
これにより、メンティーが安心して相談でき、メンターも責任を持ってサポートに取り組める環境が整い、個人と組織の活性化に貢献
【階層・目的別】カリキュラム設計の具体例
人材育成の取り組みは、すべての社員に対して同じ内容を一律に提供すれば良いというものではありません。
対象となる社員の階層や役割、そして育成を通じて達成したい目的によって、最適なカリキュラムは大きく異なります。
このセクションでは、まず代表的な対象者として「新入社員・若手社員」「中堅社員」「管理職」、そして現代のビジネス環境において特に重要性が高まっている「DX人材」の4つのカテゴリーに焦点を当て、目指すべき人材像を明確にし、具体的なカリキュラム設計の考え方とプログラム例を詳しくご紹介します。
新入社員・若手社員向け
新入社員や若手社員の育成目標は、社会人・組織人としての揺るぎない土台を築き、自ら考えて行動できる「自走力」を養うことです。
この段階で必要なのは、ビジネスマナー、ITリテラシー、会社理念・文化の理解です。
Off-JTで基礎知識を体系的に学び、OJTによる実務指導で実践力を高めるカリキュラムが有効です。
育成プログラムでは、定期的なフォローアップ研修で同期との繋がりとモチベーション維持を図ります。
また、メンター制度は、疑問や不安を解消し、新入社員が安心して成長できる環境を提供します。
これらの多角的なサポート体制により、若手社員は自信を持って業務に取り組み、自律的な成長を加速させます。
中堅社員向け
中堅社員の育成ゴールは、専門性を深掘りし、プレイヤーとして成果を出しつつ、後輩指導やチーム牽引といった「リーダーシップ」を発揮することです。
この段階では、高度な専門スキル習得のための外部研修、プロジェクトリーダーとしての実務経験、後輩指導・ファシリテーションスキル研修が効果的です。
次世代の管理職候補として、中堅社員には専門分野だけでなく、全社プロジェクトや経営課題ワークショップを通じた広い視野と、組織全体の視点から物事を捉える力を養うことが求められます。
これらの経験を通じ、専門性とリーダーシップを強化し、組織の中核を担う存在へと成長します。
管理職向け
管理職の育成ゴールは、「最高のプレイヤー」から「部下の能力と意欲を最大限に引き出し、チームとして成果を最大化するマネージャー」への役割転換です。
この転換を支援するため、部下の主体性を引き出すコーチングスキル、MBOやOKRによる目標設定、公正な評価とフィードバック技術を体系的に学びます。
さらに、チームビルディング、リスク管理、ハラスメント対策を含む労務管理といったマネジメントの基本スキル習得も重要です。
特に、他の管理職と課題を共有し実践的な解決策を議論する「アクションラーニング」は効果的です。
これにより管理職は部下の成長を支援し、組織全体のパフォーマンス向上に貢献するリーダーへと育ちます。
DX人材向け
多くの企業が関心を寄せているDX人材育成におけるゴールは、単に特定のデジタルツールを操作できるだけでなく、デジタル技術を駆使して既存の業務プロセスを主体的に改善・変革できる人材を育成することです。
この目的を達成するためのカリキュラムとしては、Power Platform(Power BI、Power Apps、Power Automate)やRPAツールといった具体的なツールの「ハンズオン研修」が非常に有効です。
研修で得た知識とスキルをすぐに実務で活かせるよう、研修後には「自部門の〇〇業務を自動化する」といった具体的な実践プロジェクトを組み合わせることが重要となります。
まずは小さな範囲で成功体験を積ませる「スモールスタート」から始め、その成果を社内で共有し、横展開していくことで、組織全体のDX推進力を着実に高めていくことができます。
このようなアプローチは、デジタル技術への抵抗感を和らげ、社員一人ひとりが自社の業務変革に貢献できるという意識を醸成する上でも効果的です。
最終的には、デジタルツールを最大限に活用し、業務効率化と新たな価値創造を実現できるDX人材を社内に増やしていくことを目指します。
「DX推進」に関する記事はこちらからお読みください。
人材育成を成功に導く組織的な仕組みづくり
これまでのセクションでは、人材育成のプロセスや具体的な手法について解説してきました。
ここからは、これらの「やり方」を組織にしっかりと根付かせ、継続的な成果を生み出すための「組織的な基盤」について深く掘り下げていきます。
どれほど優れた育成プロセスやカリキュラムを設計しても、それを実行し、文化として組織全体に浸透させる仕組みがなければ、その効果は限定的です。
このセクションでは、人材育成を成功に導く上で不可欠な組織的な仕組みとして、「教える側の育成体制」「経営層・現場・人事部門の全社的な連携体制」「学習成果を適切に評価し、キャリアに繋げる人事制度」という3つの重要な観点から具体的に解説していきます。
育成を担う「教える側」のスキルアップと体制構築
人材育成が成功するかどうかは、現場でOJTトレーナーを務める社員や、研修講師といった「教える側」の能力と熱意に大きく左右されます。
指導者によって教え方や熱意にばらつきがあると、育成効果にも差が生じてしまいます。
そのため、指導者自身に対する体系的なトレーニングを実施し、育成スキルを標準化することが非常に重要です。
具体的には、効果的なティーチング(教え方)、コーチング(引き出し方)、そしてフィードバック(伝え方)といったスキルを向上させるための研修を定期的に行う必要があります。
また、現場の指導者が「自分一人で育成の全てを担わなければならない」と悩みを抱え込むことのないよう、人事部門が積極的にサポートする体制も不可欠です。
例えば、定期的な相談窓口を設けたり、指導者同士が経験やノウハウを共有できるコミュニティや勉強会を設けたりすることで、組織全体で指導者を支え、育成の質を高めていくことができます。
経営層・現場・人材育成担当部門の連携で全社的な取り組みに
人材育成は、決して人事などの人材育成・教育担当部門だけが担うミッションではありません。
企業が持続的に成長するための重要な経営課題として、組織全体で取り組むべきテーマです。
育成施策を成功させるためには、経営層、現場の管理職、そして人材教育担当部門の三者がそれぞれの役割を明確にし、緊密に連携することが不可欠となります。
経営層は、人材育成が経営戦略や事業目標にどのように貢献するのかを明確なメッセージとして社員に示し、育成に対するコミットメントを表明することが求められます。
現場の管理職は、部下育成の重要性を深く理解し、研修参加や実務での実践機会を創出するなど、部下の成長を後押しする風土を作り出す責任があります。
そして人材育成担当部門は、これらの橋渡し役として機能し、最適な育成プログラムの企画・提供、進捗管理、そして効果測定までを一貫して行い、組織全体のハブとして機能することが期待されます。
この三者間の連携がスムーズに進むことで、人材育成は単なる「イベント」ではなく、全社的な「文化」として定着していきます。
学習成果を評価し、キャリアに繋げる人事制度
社員が多忙な業務の合間を縫ってまで自律的に学習に取り組むためには、「なぜ学ぶのか」という問いに対する明確な答え、つまり強力な動機付けが必要です。
その最も効果的な動機付けとなるのが、学びの成果が自身の評価やキャリアアップに直接的に結びつく仕組みが整備されていることです。
具体的には、習得したスキルや取得した資格を人事評価の項目に加える、あるいは昇進・昇格の要件として設定するなど、育成と人事制度を連動させる設計が重要です。
また、スキルマップなどを活用して個人の能力開発の進捗状況を可視化し、それに基づいた具体的なキャリアパスを社員に示すことで、「何を学べばどのような未来が開けるのか」を明確にすることができます。
このような仕組みは、社員の学習意欲を強力に引き出すだけでなく、組織全体の能力向上にも繋がり、企業全体の成長を加速させる原動力となるでしょう。
外部パートナーの活用で人材育成を加速させるという選択肢
社内のリソースやノウハウだけでは理想的な人材育成プロセスの構築や運用が難しい場合、外部の専門パートナーの活用は非常に有効な選択肢となります。
特にDX人材育成のように高度な専門性が求められる分野や、育成の仕組み自体をゼロから立ち上げる際には、外部の知見を借りることが成功への近道です。
このセクションでは、外部パートナーに具体的に何を依頼できるのか、そして数ある企業の中から自社に最適なパートナーを選ぶためのポイントについて解説します。
外部パートナーに依頼できることとは?
外部パートナーへの依頼範囲は、単に「研修講師を派遣してもらう」だけにとどまりません。
多くの専門パートナーは、人材育成プロセス全体を支援する多様なサービスを提供しています。
具体的な依頼内容としては、まず現状のスキルレベルや課題を客観的に分析する「アセスメント」が挙げられます。
この分析結果に基づいて、自社に最適な育成体系やカリキュラムの「設計支援」を受けることができます。
また、eラーニング動画などの「オリジナル教材作成」を依頼し、自社の業務内容に特化したコンテンツを用意することも可能です。
さらに、育成プロジェクト全体の進行管理をサポートする「PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)支援」や、研修後のスキル定着を促すところまで、伴走型で支援を受けることが可能です。
これらのサービスは、自社の状況や予算に合わせて必要なものだけを組み合わせて依頼できる柔軟性も魅力です。
失敗しないパートナー選定の3つのポイント
人材育成における外部パートナー選びは、施策の成否を左右する重要な要素です。
選定を誤ると、期待した成果が得られないだけでなく、時間やコストの無駄につながるリスクもあります。
ここでは、失敗しないための選定基準を3つのポイントに絞ってご紹介します。
POINT | 01 |
「実績と専門性」
自社の業界や育成したい特定の分野(例:DX人材育成)において、豊富な実績と深い専門知識を持っているかを確認しましょう。
過去の成功事例や提供しているサービス内容を詳しく聞くことで、そのパートナーが本当に自社の課題解決に貢献できるかを判断できます。
POINT | 02 |
「提案の具体性」
自社の課題を深く理解し、画一的なパッケージプランではなく、カスタマイズされた具体的な解決策を提示しているかが重要です。
ヒアリングを通じて、自社の状況に合わせた柔軟な提案をしてくれるパートナーを選ぶと良いでしょう。
POINT | 03 |
「伴走支援の姿勢」
研修を実施して終わりではなく、成果が出るまで責任を持って寄り添い、現場が最終的に自走できる状態を目指してくれるかを確認してください。研修後のフォローアップ体制や、現場での実践をサポートする仕組みについて具体的に確認することが大切です。
これらの視点から複数のパートナーを比較検討することで、自社にとって最適なパートナーを見つけることができるでしょう。
まとめ
これまで、人材育成における「研修が単発のイベントで終わってしまう」「実務とかけ離れていて学習意欲が湧かない」「効果測定が曖昧で投資対効果を説明できない」という3つの失敗パターンとその原因について解説してきました。
これらの課題を解決し、現場で本当に役立つ人材を育成するためには、体系的なアプローチが不可欠です。
その解決策として提示したのが、「現状把握と課題の可視化」「育成ゴールと人材像の具体化」「実践的カリキュラムの設計」「効果測定と継続的な改善サイクル」という4つのステップからなる人材育成プロセスです。
このプロセスをPDCAサイクルとして継続的に回すことで、場当たり的な育成ではなく、戦略的で成果につながる人材育成が可能になります。
そして、人材育成の最終的なゴールは、単に社員のスキルレベルを向上させることだけではありません。
社員一人ひとりが自ら考え、行動し、新しい課題に挑戦しながら継続的に成果を出せる「自走できる組織」を作ることこそが、真の目的です。
この記事が、皆さんの会社の人材育成を見直し、社員がイキイキと成長できる組織づくりに向けた一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
「自走できる組織」づくりを実現するデジタル人材育成サービス(株式会社システナ)
人材育成プロセスを把握し、どのようなカリキュラム設計を行えばよいかはわかったものの、自社では「人材育成担当者のリソース不足」や「専門知識の不足」といった課題を抱えている方も多いと思います。
そこで株式会社システナでは、スキル診断による現状把握から、企業ニーズに合わせた最適な教育カリキュラムの立案、実践的な研修の実施、研修後の効果測定まで、人材育成プロセスの一気通貫でサポートしております。
システナの「デジタル人材育成サービス」に関する詳細はこちら
特に、Power Platform(Power BI, Power Apps, Power Automate)やRPAツールといったデジタル技術の習得においては、実務に直結するハンズオン形式のトレーニングを豊富に提供し、お客様の業務内容に合わせて柔軟にカスタマイズが可能です。
研修を「やりっぱなし」にせず、習得スキルを実務で確実に活用できるよう、PMOサービスによるプロジェクト推進サポートや、研修後のスキル定着支援を通じて伴走します。
またシステナは、一般社団法人日本PMO協会が主催する「PMOアワード2025」にて【優秀賞】を受賞しており、専門知識を持ったチームが支援をしております。
人材育成でお悩みの方はぜひ一度、お気軽にご相談ください。